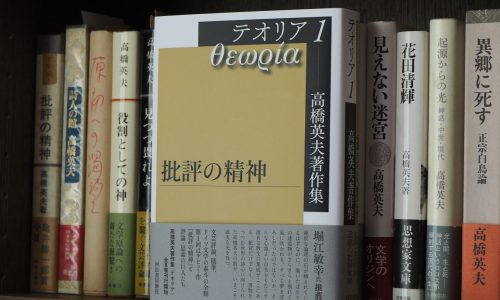前回の毘沙門堂で触れたように、賀茂川の西、鞍馬口近くに鎮座している上御霊神社は、平安京以前にあった上出雲寺跡に創建された神社です。正式には御霊神社といいますが、下御霊神社と区別するために上御霊神社と呼ばれています。
桓武天皇は即位後ほどなく大和国を離れ山城国に都を移すことにし、延暦三年(七八四)長岡京を造営しますが、遷都の中心的役割を任されていた藤原種継が暗殺され、桓武天皇はそれを弟・早良親王の仕業とし、親王を流罪の刑に処します。親王は無実を訴え自ら食を断ち、淡路島への移送中亡くなってしまうのですが、それから桓武天皇の身近な人が相次いで亡くなったり、自然災害が起こるなどの異変が続いたことから、それを早良親王の祟りによるものと畏れ、桓武天皇は平安京に都を遷すとすぐに都の鬼門に位置する当地に早良親王を王城鎮護の神としてお祀りしました。それが上御霊神社の始まりと言われています。
その後、井上大皇后(聖武天皇の娘、桓武天皇の父光仁天皇の后)、他戸親王(光仁天皇と井上皇后の息子)、藤原大夫(藤原広嗣)、橘大夫(橘逸勢)、文大夫(文屋宮田麿)が合祀され、さらに火雷神(菅原道真)と吉備聖霊(吉備真備)が加わり、御祭神は八柱になりました。これら八柱は政争に巻き込まれるなどして非業の死を遂げた人たちで八所御霊と呼ばれます。
平安時代は自然災害や疫病が頻繁に起こりましたが、その原因を非業の死を遂げた人の怨霊によるものと考え、それを鎮めて御霊とし、手厚くお祀りすることによって強力な守護神に転じ、平穏無事がもたらされるという御霊信仰が生まれました。鎮魂のための儀式を御霊会といい、宮中の行事として行われましたが、次第に民衆の間にも拡がり、そこに神輿の渡御や踊りなどが加わり、今各地で行われている祭へと発展していったとされています。
人は死ぬとどうなるのか。その謎は永遠に解き明かされることはないのかもしれませんが、霊魂の存在に対する信仰は縄文時代あたりに遡ることができそうです。縄文人は手足を折り曲げて埋葬する屈葬でした。これは死者の魂が浮遊し悪さをするのを防ぐためと考えられています。その後の古神道では神様は和魂と荒魂の二面性を持つものとされます。この荒魂は荒ぶる神、災いを引き起こす神ということで、桓武天皇が畏れた怨霊に近い性質を持っていますから、平安時代に盛んになった御霊信仰の起源は相当前に遡ることができるのではないでしょうか。
写真下、堂々たる四脚門は伏見城から移築されたと伝わります。
こちらの本殿は、享保十八年(一七三三)に寄進された宮中の賢所御殿を、昭和になってから復元したものです。築年数は浅いですが、風格ある建物です。
ちなみにここは応仁の乱発祥の地です。
応仁元年(一四六七)、御霊神社の森に布陣した畠山政長を畠山義就の軍が攻め「御霊合戦」が始まります。畠山政長は神社拝殿に火をかけて逃走。それをきっかけに戦乱は応仁・文明の乱に拡大したのです。
上御霊神社の社殿も文明十年(一四七八)に焼失し、社殿はその後足利氏により再建されました。
京都の重要な歴史の転換点に関わった神社のせいか、境内は荘重な空気に包まれています。全盛期には現在の二倍近い広さがあり、御霊の森と呼ばれていたそうです。
出雲氏時代からの歴史を思い、静かな境内にしばし身を置きました。