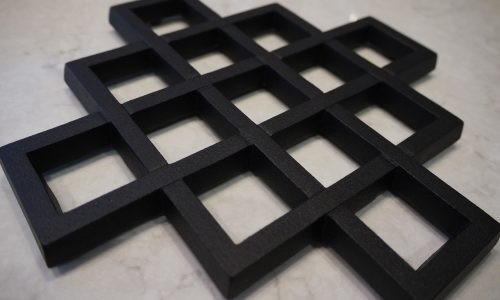宗教、文化、芸術、芸能の粋が集まり見事な結晶を残しているかつての都、奈良や京都がすばらしいのは誰もが認めるところで、私も折に触れてそうした土地を訪ねては、結晶の華に酔いしれる一人ですが、都周辺の、いわゆる中間地帯には都とはまた違った魅力があります。もう十年も前になってしまいましたが、京都の東に隣接する滋賀県(近江国)の魅力に取り憑かれて書いた「近江古事風物誌」は、まさにその中間地帯の風土を描いたもので、そこで出会った謙虚な美の数々はいまも私の心の糧になっています。
今日取り上げる楊谷寺も、そうした中間地帯にある古刹。近年紫陽花の寺として知られるようになりました。
京都の西に連なる西山連山の南、大山崎に近い浄土谷堂ノ谷の山中に楊谷寺が開かれたのは大同元年(八〇一)と伝わります。開祖は清水寺を開いたことでも知られる延鎮。夢のお告げで西山に入った延鎮は柳(楊)が生い茂る岩の上に生身の十一面千手千眼観音菩薩を感得、そこにお堂を建ててお祀りしたことに始まるとのことで、西の清水と呼ばれることもあります。
その後楊谷寺を訪れた空海は、お堂脇で親猿が子猿のつぶれた眼を湧き水で懸命に洗っているところに遭遇。快復を願い十七日間祈祷したところ、満願の日に子猿の眼が開いたことから、その湧き水は霊水として崇められるようになり、多くの人がお詣りに訪れるようになったのだとか。
江戸時代には霊元天皇の眼病が治癒、それ以後霊水を天皇家に献上、そのご縁で天皇家から下賜された宝物も多数伝わります。
その霊水は独古水と呼ばれ、現在もこのようにいただくことができます。
空海が棒のようなもので地面をつついたところ水が出たというような伝説は各地に伝わります。楊谷寺の霊水伝承も決して珍しいものではありませんが、各地の講が寄進した灯篭や橋などから、楊谷寺への厚い信仰が今なお盛んであることがわかります。ちなみに楊谷寺の講は関西を中心に各地にあり、京都府では伏見、宇治、京田辺、城陽、精華、木津、大阪府では東淀川区、西淀川区、高槻市、寝屋川市、守口市といった具合で、その分布を見ていると、木津川、宇治川、淀川といった河川が信仰の拡がりと無縁ではないような気がしてきます。
山に食い込むように建つ楊谷寺はいくつもの伽藍を擁しています。現在の建物は江戸時代以降のもので、上書院に至っては明治後期のものですが、多くの人がお詣りに訪れ、手を合わせてきたその思いの重み故か、それ以上の時間の経過を感じさせます。
本堂にお祀りされている御本尊は毎月十七、十八日のみご開帳になります。あいにく拝観は叶いませんでしたが、御本尊に繋がる五色の結縁紐を手にとり、しかと手を合わせてまいりました。
書院からは江戸時代中頃に造られた浄土苑を見ることができます。山の斜面を利用し、阿弥陀如来や不動明王など十三仏に見立てた石が配された浄土苑は縦方向を意識させられる庭で、迫力を感じます。
書院に続く階段を上がり上書院に移動すると、今度は庭を別の向きから眺めることができます。
上書院は二層になっており、二階から見下ろす庭もまた格別です。今は青紅葉の美しい時期ですが、紅葉もまた見事でしょう。
紫陽花を見ながら長い上りの渡り廊下を進み、北の奥の院へ。
奥の院のお堂は大正元年(一九一二)に創建され、その後火災で焼失したため昭和五年(一九三〇)に再建されたものですが、そこにお祀りされている観音像は次のような謂われを持っています。
百十三代の東山天皇(一六七五~一七一〇)と新崇賢門院との間に生まれた皇子が次々に亡くなったことから、無事出産した際には観音様をお祀りする旨、御本尊に誓いをたてて祈願されたところ、後に百十四代となられる中御門天皇が誕生しました。ところが中御門天皇が幼いとき両親が崩御されたことから、追善のために中御門天皇が観音像を作られたとのこと。詳しい経緯はわかりませんが、二百年近く経ってその観音様のためのお堂が造られたということのようです。
奥の院のさらに奥には、奥の院の鎮守・眼力稲荷がお祀りされ、神仏習合の名残を伝えています。
奥の院周辺にも色とりどりの紫陽花が。池にはモリアオガエルの卵もあり、姿は見えずとも鳴き声が響き渡っています。
奥の院から下ってくる途中に、もう一つの鎮守があります。伏見稲荷から勧進されたという当山の守り神で、先見の明を授けてくださる神様だそうです。それこそ必要なものということで、ここでもしかと手を合わせてまいりました。
明治になりその多くが破壊されてしまった神仏習合の聖地ですが、ここ楊谷寺のように中心部から一歩外れたところには案外とその名残が見られます。神と仏が混在する祈りこそ、日本独自の信仰の形ですから、ここでその生き残りに出会えたのは何より嬉しいことでした。